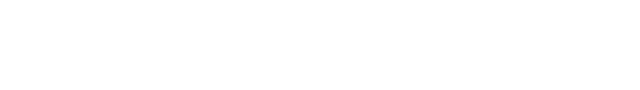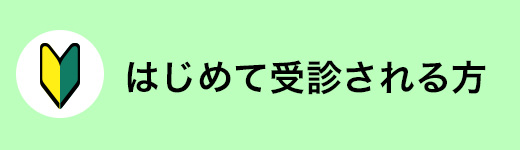きし内科クリニック通信2025年6月号(113号)【 梅雨の時季の咳「咳ぜんそく」】
【 梅雨の時季の咳 「咳ぜんそく」 】
きし内科クリニック院長の岸 雅人です。きし内科クリニック通信 第113号を発行いたしました。
本号では、梅雨の時季の咳「咳ぜんそく」のお話を掲載いたします。
新型コロナウイルスの流行により子どもたち(特に幼児)が感染対策を徹底した結果、免疫を持たない子こどもたちが多くなりました。子どもたちが免疫を持たないため、最近の2年間は子どもの感染症(RSウイルス感染症、溶連菌、マイコプラズマ、手足口病、インフルエンザなど)の大流行が続きました。子どもたちが一通りの細菌・ウイルスに感染した結果集団免疫を獲得して、今年に入ってからは大きな感染症の流行はみられていないようです。細菌・ウイルス感染を乗り越えて抗体を作ることが、子どもの成長に必要なのだなとしみじみと実感しています。
今年も梅雨の季節がやってきました。今年の日本気象協会の「梅雨入り予想」では、九州北部~関東甲信は6月上旬に梅雨入りし、平年並みの梅雨入りとなるようです。平年より遅い6月下旬の梅雨入りとなった昨年と比べると、今年は全国的に梅雨入りの早まるところが多くなるそうです。
毎年梅雨の季節に咳が長引く方、風邪薬を内服しても咳だけが長びいておさまらない方はいらっしゃいませんか。梅雨の時期、秋の台風の時期など、季節の変わり目の咳でお困りの方は、「咳ぜんそく」かもしれません。
「気管支ぜんそく」とは、様々な原因で気管(空気の通り道)に、慢性の長びく(好酸球浸潤を伴う)炎症が起こる病気です。つまり、「気管支ぜんそく」=「気管支炎が長く続き、なかなか治らない病態。」と大まかに言い換えることが出来ます。
主な症状は、息苦しさ、咳、痰、のどや胸の違和感・いがいが感、鼻水、鼻づまりなどになります。
「気管支ぜんそく」の中で、息苦しさを伴わず、咳を主な症状とするものを、「咳ぜんそく」といいます。
「気管支ぜんそく」「咳ぜんそく」を引き起こす原因は、以下のように大きく5つに分けられます。
①気候の変化・激しい運動(気温、湿度、気圧の変化などが、気管を刺激するため。)
②アレルギー・刺激物質の吸入(ほこり、花粉、カビ、喫煙、香水などが、気管を刺激するため。)
③疲労、精神的ストレス(心を支配する自律神経が気管に通じているため。)
④風邪(風邪のウイルスや菌が気管に炎症を起こし、気管の粘膜が刺激を受けやすくなるため。)
⑤妊娠・出産(妊娠による体のホルモン環境の変化や、育児などによる生活環境の急激な変化が要因。)
6月の梅雨の時期は、以下のように咳ぜんそくを引き起こしやすい要因がそろっています。
①気温・気圧・湿度の変化が大きい。
②アレルギー物質である「ダニ」「カビ」が発生しやすい(湿度が高いため)。
③イネ科の花粉「ネズミホソムギ」「カモガヤ」「オオアワガエリ」などが、江戸川の河川敷などから多く飛散する。
④新年度で職場や住環境が変わることによるストレス(五月病)
④夏かぜ「アデノウイルス」「エンテロウイルス」などの流行。
ぜんそくによる咳の場合は、特に以下の条件でひどくなることが多いといわれています。
①夜布団に入るときや、寝ているとき、朝起きたとき。
②お風呂あがり、電車に乗るときなど、急激に気温や湿度や気圧が変化するとき。
③運動したとき、しゃべるとき、歌うとき、ラーメンを食べるとき、強いにおいをかいだときなど、気管が刺激をうけるとき。
咳ぜんそくの治療は、気管支ぜんそくの治療と同じで、吸入ステロイド薬と吸入気管支拡張薬が中心となります。ステロイド薬は副作用が心配というイメージがあるかもしれませんが、吸入や点鼻のステロイド薬は、内服のステロイド薬と異なり、お子様や妊婦さんが使用しても安全ですので安心してください。
長引く咳、止まらない咳でお困りの方は、ぜひ当院にご相談下さい。
2025-05-26 12:52:08