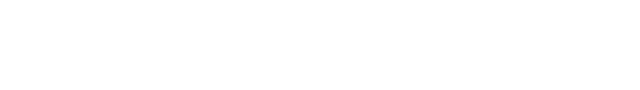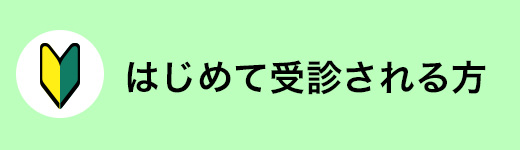きし内科クリニック通信2025年5月号(第112号)【 「イネ科の花粉症」の季節です】
【 「イネ科の花粉症」の季節です 】
きし内科クリニック院長の岸 雅人です。
きし内科クリニック通信 第112号では、今年もイネ科の花粉症のお話を掲載いたします。
新型コロナウイルスの流行により子どもたち(特に幼児)が感染対策を徹底した結果、免疫を持たない子こどもたちが多くなりました。子どもたちが免疫を持たないため、最近の2年間は子どもの感染症(RSウイルス感染症、溶連菌、マイコプラズマ、手足口病、インフルエンザなど)の大流行が続きました。子どもたちが一通りの細菌・ウイルスに感染した結果集団免疫を獲得して、今年に入ってからは大きな感染症の流行はみられていないようです。細菌・ウイルス感染を乗り越えて抗体を作ることが、子どもの成長に必要なのだなとしみじみと実感しています。
あたたかくなり、江戸川の河川敷の散歩がとても心地よい季節になりました。
今年は昨年と比較してスギ・ヒノキの飛散量が多くはなかったようです。しかしイネ科の花粉症をお持ちの方はこれからが花粉症の本番です。イネ科の花粉の飛散は例年4月上旬ごろからから始まり、5月以降にピークを迎えるためです。
江戸川の河川敷に多くのイネ科の植物が植生しています。現在の市川市周辺の江戸川堤防では、イネ科の「ネズミホソムギ」を中心とする寒地型の外来牧草類が広く分布しています。
「ネズミホソムギ」(鼠細麦:イネ科ネズミムギ属)は、ネズミムギとホソムギの中間型の帰化植物で、別名を「イタリアンライグラス」といいます。緑化や飼料用に栽培される一年草または越年草で、丈は40-70cmになります。
「ネズミホソムギ」の花粉の飛散時期は5月中旬~8月上旬(ピークは5月中旬~6月下旬)になります。
その他の花粉症を引き起こすイネ科の植物に、「カモガヤ」「オオアワガエリ」があります。カモガヤの別名を「オーチャードグラス」、オオアワガエリの別名を「チモシー」といいます。ともに飼料用(主に採草用)として最も広く利用され、沖縄を除く全国で栽培されています。花粉の飛散時期は5月~8月になります。空き地・道端・畑の周辺などに、ほぼ日本全域に生息しています。
イネ科の花粉はスギ花粉のように広範囲に飛散しません。スギ花粉は10km以上飛散する一方、イネ科の花粉は多くて200m程度しか飛散しません。江戸川の河川敷を散歩すると花粉症の症状が悪くなる人は、イネ科の「ネズミホソムギ」の花粉症の可能性が高いと考えます。
ところで、イネ科の花粉症に罹患すると、口腔アレルギー症候群(花粉-食物アレルギー症候群)を引き起こす場合があることが知られています。口腔アレルギー症候群とは、果物や野菜を食べた際、約15分以内に唇や口の中にイガイガ感・かゆみ・腫れなどのアレルギー症状があらわれる病気です。特定の花粉に含まれる抗原物質と特定の果物・野菜に含まれる抗原物質で似ているものがあります。そのため特定の花粉に対してアレルギーを起こすと、特定の果物・野菜に対してもアレルギーを引き起こしてしまうことがあり、イネ科の花粉症に罹患すると特定の食物の口腔アレルギーを生じる原因になります。イネ科の花粉に含まれる抗原物質と似ている抗原をもつ食物は、ウリ科(メロン、スイカ)、ナス科(トマト、じゃがいも)、マタタビ科(キウイ)、ミカン科(オレンジ)、マメ科(ピーナッツ)が知られています。これらの果物や野菜を食べた後に口の中がイガイガする人は、イネ科の花粉症の可能性があります。
ゴールデンウイークが明けても花粉症の症状が続く方、血液採取によるアレルギー検査を希望の方、ダニやスギ花粉症の舌下免疫療法をご希望の方は、当院にお気軽にご相談ください。
2025-05-02 11:49:06