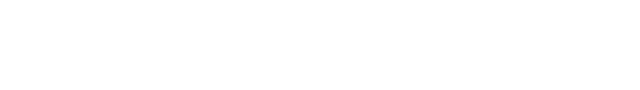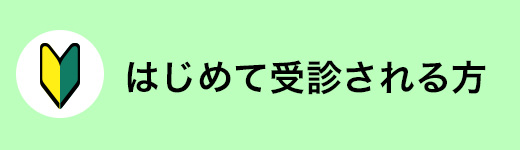小児科
小児科診療
小児ぜんそく
小児ぜんそくは、子どもに多く見られる呼吸器の慢性疾患で、気道が炎症を起こしやすくなり、発作的に咳や喘鳴(ぜんめい)、呼吸困難が起こるのが特徴です。原因は遺伝的な体質(アトピー素因)や、ダニやハウスダスト、花粉、ウイルス感染、運動などさまざまな環境因子が関係しています。小児ぜんそくは、夜間や早朝に症状が悪化しやすく、特に風邪をひいたときなどに発作が起こりやすくなります。
治療の基本は、発作の予防と症状のコントロールです。吸入ステロイド薬を中心とした長期管理薬によって炎症を抑え、必要に応じて発作時には短時間作用型の気管支拡張薬を使用します。また、生活環境の整備も大切で、アレルゲンの除去や禁煙、適度な運動、規則正しい生活習慣の確立が重要です。
小児ぜんそくは成長とともに症状が軽くなったり、治まることもありますが、一部は成人喘息に移行することもあります。早期の診断と適切な治療、家族の理解と支援によって、子どもが日常生活を快適に過ごし、将来の健康を守ることができます。
小児の長引く咳
小児の咳が長引く場合、親としては心配が尽きません。咳が2週間以上続く場合を「遷延性咳」、8週間以上続く場合を「慢性咳」と呼びます。原因としては、かぜの後に気道の過敏性が残る「感染後咳嗽」、アレルギー性疾患(気管支喘息やアレルギー性鼻炎)、副鼻腔炎(いわゆる蓄膿症)などが挙げられます。特に喘息は、夜間や早朝に悪化する咳や、運動後の咳として現れることが多く、注意が必要です。
また、マイコプラズマや百日咳などの感染症も長引く咳の原因となることがあります。百日咳はワクチン接種で予防できますが、免疫が完全ではないため、年長児でも発症することがあります。その他、異物誤嚥(気道に異物が入る)や先天性の気道異常もまれに原因となります。
診断には、問診や診察に加え、胸部X線や血液検査、アレルギー検査が行われることもあります。治療は原因に応じて、吸入ステロイド薬や抗生物質、抗ヒスタミン薬などが使われます。長引く咳がある場合は、早めに小児科を受診し、正確な診断と適切な治療を受けることが大切です。家庭では、部屋の加湿や換気、受動喫煙の回避など、環境を整えることも重要です。
小児アレルギー診療
小児アレルギー診療は、子どもの成長や生活の質に大きく影響するアレルギー疾患に対して、的確な診断と治療を行う医療分野です。代表的な疾患には、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、アレルギー性鼻炎などがあり、近年その発症率は増加傾向にあります。特に乳児期や幼児期に発症することが多く、年齢によって症状や原因が異なるため、年齢ごとの対応が求められます。
診療においては、家族歴や生活環境を含む詳細な問診、血液検査などによる原因アレルゲンの特定、重症度評価などが重要です。治療は、薬物療法(抗ヒスタミン薬、ステロイドなど)に加え、原因アレルゲンの回避や食事療法、皮膚のスキンケアなど多面的に行われます。また、食物アレルギーに対しては、誤食時の対応や学校・保育所との連携も不可欠です。
さらに、近年はアレルゲン免疫療法や早期経口摂取による耐性獲得など、新しい治療や予防法も注目されています。小児アレルギー診療では、子どもと家族の生活全体を支える視点が大切であり、保護者との信頼関係や継続的なフォローアップも診療の要となります。
小児の風邪
小児の風邪(かぜ)は、乳幼児から学童期の子どもに一般的に見られる感染症で、年間に何度もかかることがあります。風邪の主な原因はウイルスであり、特にライノウイルス、コロナウイルス、RSウイルスなどが多くを占めます。症状としては、発熱、くしゃみ、鼻水、咳、のどの痛みなどがみられます。多くの場合、軽症で済み、数日から一週間程度で自然に回復します。
小児は免疫力が未発達なため、風邪にかかりやすく、また保育園や学校などで他の子どもと接する機会が多いことも感染の一因です。治療は主に対症療法であり、十分な休養と水分補給、必要に応じて解熱剤や咳止めなどを使います。抗生物質は細菌感染には有効ですが、風邪の多くはウイルス性のため、通常は使用しません。
予防には、手洗いやうがいの徹底、マスクの着用、部屋の換気などが重要です。また、親や周囲の大人が体調管理に注意し、子どもが風邪をひいた際には無理をさせず、早めに休ませることが大切です。風邪が長引く場合や、高熱、呼吸困難などの症状がある場合は、早めに医療機関を受診することが望まれます。
小児の胃腸炎
小児の胃腸炎は、主にウイルスや細菌の感染によって引き起こされる消化器の炎症疾患で、嘔吐や下痢、腹痛、発熱などが主な症状です。アデノウイルス、エンテロウイルス、ノロウイルス、溶連菌など原因となることが多く、夏季や冬季に流行しやすい特徴があります。感染力が強く、集団生活をする乳幼児や学童での感染拡大が問題となります。
診断は症状の経過や便の状態、場合によっては迅速検査で行われますが、重症化を防ぐために早期の対応が重要です。治療の基本は脱水予防であり、経口補水液を用いて水分と電解質の補給を行います。嘔吐が強い場合は少量ずつ頻回に与えることが推奨されます。抗菌薬は細菌感染が明確な場合を除き、通常は使用されません。
また、乳幼児は脱水症状に陥りやすいため、皮膚の乾燥や尿量の減少、唇の乾燥などの脱水のサインに注意が必要です。予防としては手洗いの徹底や適切な衛生管理が重要で、特に保育施設や学校での感染対策が求められます。
重症例では入院が必要になることもあり、特に乳児や基礎疾患のある子どもは慎重な管理が必要です。総じて、小児の胃腸炎は適切な水分補給と衛生対策によりほとんどが回復しますが、症状の悪化や長引く場合は医療機関を受診することが大切です。
小児感染症
小児感染症は、子どもに特有または多く見られる感染症の総称であり、ウイルスや細菌、真菌などさまざまな病原体によって引き起こされます。乳幼児や学童期の子どもは免疫機能が未成熟であるため、感染症にかかりやすく、重症化しやすい特徴があります。
代表的な小児感染症には、風邪やインフルエンザ、水痘(みずぼうそう)、麻疹(はしか)、百日咳、おたふくかぜ、ロタウイルス感染症などがあります。これらの感染症は、咳やくしゃみ、接触を通じて容易に感染が広がるため、保育園や学校での集団感染が問題になることがあります。
感染予防には、手洗いやうがい、マスクの着用、適切な換気が重要です。また、予防接種によって多くの小児感染症の発症や重症化を防ぐことが可能となっています。日本では定期予防接種制度が整備されており、麻疹・風疹混合ワクチン(MRワクチン)や水痘ワクチン、百日咳ワクチンなどが推奨されています。
治療は感染症の種類や症状に応じて行われ、ウイルス性の場合は対症療法が中心となりますが、細菌感染症では抗生物質が用いられます。重症化した場合には入院治療や集中治療が必要となることもあります。
小児感染症は適切な予防と早期治療によって健康被害を最小限に抑えられるため、保護者や医療従事者は感染症の知識を深め、適切な対策を行うことが大切です。