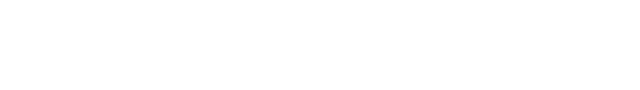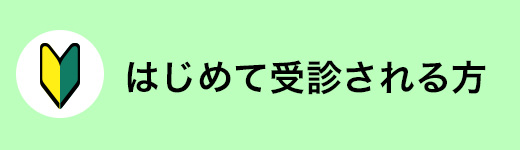内科
内科診療
風邪
風邪(鼻づまり、鼻やのどの粘膜の乾燥、くしゃみ、鼻水、のどが痛む、せきが出る。などの症状)風邪は、鼻からのどまでの上気道を中心とする部分に、ウイルスや細菌が感染して急激に起こる炎症です。
実際に風邪をひくと、気管や気管支などの下気道にも炎症が広がっていく場合も少なくありません。原因になる病原体はたくさんありますが、その80~90%はウイルスで200種以上にのぼります。疲労やストレス、睡眠不足、栄養バランスの偏り、寒さ、乾燥などの要因が重なると発症しやすくなることが知られています。
高血圧
高血圧症は、血圧が慢性的に正常範囲を超えて高い状態を指します。収縮期血圧が140mmHg以上、または拡張期血圧が90mmHg以上の場合に診断されます。自覚症状が少なく、放置すると心筋梗塞や脳卒中、腎障害などの重大な合併症を引き起こす可能性があります。原因は本態性高血圧が多く、遺伝や生活習慣が関与しています。予防と治療には、減塩・適度な運動・禁煙・節酒・体重管理が重要です。必要に応じて降圧薬が用いられます。継続的な血圧管理が健康維持に不可欠です。
脂質異常症
脂質異常症(ししついじょうしょう)は、血液中の脂質(コレステロールや中性脂肪)の値が正常範囲を超えて異常となる状態を指します。主なタイプには、LDLコレステロール(悪玉コレステロール)の増加、HDLコレステロール(善玉コレステロール)の低下、中性脂肪の増加があります。これらの異常が長期間続くと、動脈硬化が進行し、心筋梗塞や脳卒中といった重大な疾患のリスクが高まります。
原因には、食生活の乱れ(高脂肪・高カロリー食)、運動不足、肥満、過度の飲酒、喫煙、遺伝的要因などが関与します。症状は自覚されにくく、健康診断で発見されることが多いのが特徴です。
治療には、まず食事療法と運動療法が基本となり、生活習慣の改善が求められます。改善が難しい場合には、スタチンなどの脂質を下げる薬が処方されることもあります。早期発見と継続的な管理が重要であり、定期的な血液検査と医師の指導のもと、動脈硬化予防に努めることが大切です。
糖尿病
糖尿病とは、血糖値(血液中のブドウ糖濃度)が病的に高い状態をさす病気です。
糖尿病には「インスリン依存型(I型)糖尿病」と「インスリン非依存型(II型)糖尿病」の2つのタイプがあります。
「インスリン依存型(I型)糖尿病」は、ウイルス感染や自己免疫により膵臓が破壊されておきる糖尿病です。全体の5%の方が、こちらのタイプの糖尿病です。
「インスリン非依存型(II型)糖尿病」は、遺伝要因にくわえて、食べ過ぎ、運動不足、ストレスが加わって発症する糖尿病です。95%の糖尿病がこのタイプです。
糖尿病は深刻な合併症(神経障害、網膜症、腎症、動脈硬化症など)を引き起こすことがあり、最悪の場合は、死に至る危険な病気です。早めの治療・対策が必要です。
高尿酸血症
高尿酸血症とは、血液中の尿酸値が基準値(男性で7.0mg/dL、女性で6.0mg/dL)を超えた状態を指します。尿酸はプリン体の代謝によって生じる老廃物で、腎臓から排泄されますが、過剰な生成や排泄障害により蓄積すると高尿酸血症になります。主な原因には、プリン体を多く含む食品の過剰摂取、飲酒、肥満、腎機能低下などが挙げられます。高尿酸血症は痛風発作や腎障害、動脈硬化のリスクを高めるため、生活習慣の改善や必要に応じた薬物療法が推奨されます。
胃腸炎
胃腸炎とは、胃や腸に炎症が起きる病気で、ウイルスや細菌、寄生虫、食中毒、不適切な飲食などが原因となります。主な症状には、腹痛、下痢、吐き気、嘔吐、発熱などがあり、体内の水分や電解質が失われることで脱水症状を引き起こすこともあります。
ウイルス性胃腸炎は冬に流行しやすく、特にノロウイルスが代表的な原因です。感染力が非常に強いため、手洗いや消毒などの予防が重要です。細菌性胃腸炎は、サルモネラ菌やカンピロバクターなどの汚染された食品が原因で発症します。
治療は原因によって異なりますが、基本的には水分補給と安静が中心です。症状が重い場合や高熱、血便がある場合は医療機関を受診し、必要に応じて薬の処方を受けることが大切です。
予防には、手洗いの徹底、食品の十分な加熱、衛生的な調理環境の維持が効果的です。特に子どもや高齢者など、免疫力が弱い人は重症化しやすいため注意が必要です。
生活習慣病
生活習慣病とは、日々の生活習慣が深く関わって発症する病気の総称です。代表的なものには、高血圧症、糖尿病、脂質異常症(高脂血症)などがございます。これらの病気は、偏った食生活、運動不足、喫煙、過度の飲酒、ストレスなどが主な原因とされています。
生活習慣病は、初期の段階では自覚症状がほとんどない場合が多く、気が付かないうちに進行してしまうことがあります。そのため、症状が現れたときにはすでに重篤な状態となっていることも少なくありません。たとえば、動脈硬化が進行することにより、心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる重大な病気を引き起こす可能性もあります。
このような生活習慣病を予防するためには、日頃からの健康管理が重要です。バランスの取れた食事を心がけ、適度な運動を取り入れ、十分な睡眠を確保することが大切です。また、定期的な健康診断を受けることで、早期発見・早期治療が可能となります。
生活習慣病は、自分自身の心がけ次第で予防・改善ができる病気です。日々の生活の中で少しずつでも良い習慣を積み重ね、健康な体を維持していきましょう。
漢方治療
漢方薬は症状をおさえる効果に優れることが多く、原因のはっきりしない症状に対しては、西洋薬治療に漢方薬を加えることで、著しい治療効果を認める場合が多くみられます。
体力不足、疲れ、ストレス、胸苦しさ、冷え、下痢、のぼせ・ほてり、むくみ、慢性の咳などの症状に対し漢方治療の効果を実感する機会が多いため、必要に応じて漢方薬の処方を行います。